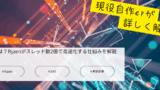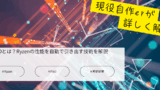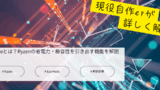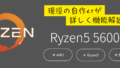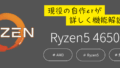どうも、ジサ郎です。
Ryzen 7 4750Gは、Zen 2アーキテクチャを採用した「Renoir」世代のAPUとして2020年に登場しました。
8コア16スレッド構成を持ちながら、Radeon Vega 8を統合した設計により、CPUとGPUの両面でバランスの取れた性能を発揮します。当初はOEM向けに限定提供され、自作市場では入手が難しかったものの、その高い汎用性と安定した動作から多くの注目を集めました。
前世代のRyzen 3000Gシリーズから大きく進化し、シングル・マルチ性能の向上に加え、内蔵GPUの描画効率も改善。グラフィックボードなしでのライトゲーミングや動画編集も可能となり、省スペースPCや業務用PCの構築に適した選択肢といえます。
この記事では、Ryzen 7 4750Gの特徴や性能、搭載機能、相性問題まで徹底的に解説していきます。
概要
Ryzen 7 4750Gは、AMDが2020年7月に投入した「Ryzen PRO 4000G」シリーズの上位モデルであり、Zen 2アーキテクチャをベースにした「Renoir」世代のAPUです。
8コア16スレッド構成を備え、従来のRyzen 3000Gシリーズ(Zen+世代)から大きく飛躍した性能を持ちます。
製造プロセスは7nmへ移行し、電力効率の改善とクロック向上により、ビジネス用途からクリエイティブ作業まで幅広いシーンで安定した処理能力を発揮しました。
内蔵GPUにはRadeon Vega 8を搭載し、CU数は据え置きながら動作クロックが最大2.1GHzへと向上。これにより、動画再生やフルHD解像度でのライトゲーミングがグラフィックボード不要で可能となり、コストを抑えたPC構築を実現しています。
ただし当初はOEM向け限定提供であり、一般自作市場では入手が難しいCPUでした。そのため、法人向けPCやメーカー製PCへの採用が中心で、後に流通が広がることで自作ユーザーからの注目も高まりました。
Ryzen 7 4750Gは、Zen 2世代における「高性能かつ扱いやすい万能型APU」として位置づけられ、AM4環境を活かしたアップグレード需要にも応える存在となっています。
スペック表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アーキテクチャ | Zen 2 + Vega iGPU(Renoir) |
| コア数 | 8コア |
| スレッド数 | 16スレッド |
| ベースクロック | 3.6 GHz |
| 最大ブーストクロック | 最大 4.4 GHz |
| L1キャッシュ(命令用) | 32 KB × 8コア = 256 KB |
| L1キャッシュ(データ用) | 32 KB × 8コア = 256 KB |
| L2キャッシュ | 512 KB × 8コア = 4 MB |
| L3キャッシュ(CCD単位) | 8 MB |
| 3D V-Cache容量 | – |
| 合計L3キャッシュ容量 | 8 MB |
| TDP | 65 W |
| 対応ソケット | AM4 |
| 内蔵GPU | Radeon Vega 8(8CU、最大 2.1 GHz) |
- L1キャッシュの総容量は、512KB(命令用256KB+データ用256KB)。命令用とデータ用は各コア専用で、合計値は全8コアの総和。
- L3キャッシュ(CCD単位)は、モノリシックCCD構造で8MBが搭載されています。
- 3D V-Cache容量は、X3Dモデル専用のため非搭載です。
搭載されている機能
Ryzen 7 4750Gは、Zen 2アーキテクチャを採用したAPUとして、CPUとGPUの両面でバランスの取れた機能を備えています。
8コア16スレッド構成による強力な演算性能に加え、内蔵GPU「Radeon Vega 8」を搭載することで、外部グラフィックボードなしでも快適なマルチメディア処理やライトゲーミングを実現します。
さらにPrecision Boost 2やPBO、Pure PowerなどAMD独自の技術をサポートし、性能と省電力性を高次元で両立。本セクションでは、Ryzen 7 4750Gが備える主要な機能について詳しく解説していきます。
Simultaneous Multi-Threading(SMT)搭載
Ryzen 7 4750Gは、AMDのSimultaneous Multi-Threading(SMT)技術を搭載しており、1つの物理コアで2つのスレッドを同時処理できます。
これにより8コア構成の4750Gは16スレッドを扱うことが可能となり、マルチタスク性能が大幅に向上します。動画編集や3Dレンダリングといったクリエイティブ用途はもちろん、複数のアプリケーションを同時に動かす場面でも効率的にリソースを活用できます。
日常的な処理から業務用途まで幅広い環境で快適な作業を実現できる点が、SMTの大きな強みです。
Precision Boost 2(PB2)搭載
Ryzen 7 4750Gは、自動クロック制御機能「Precision Boost 2(PB2)」を搭載しています。これは動作中のコア数や温度、電力状況をリアルタイムで監視し、必要に応じてクロックを自動で引き上げる仕組みです。
従来のように特定のコアだけでなく、全コアに対して柔軟にブーストが行えるため、シングルスレッド性能からマルチスレッド性能まで効率よく引き出せます。
ユーザーが特別な設定をしなくても恩恵を受けられるため、ゲームやビジネス用途、クリエイティブ作業など幅広いシーンで快適な動作を実現します。
Precision Boost Overdrive(PBO)搭載
Ryzen 7 4750Gは、PB2を拡張した「Precision Boost Overdrive(PBO)」に対応しています。PBOは、マザーボードの電力供給や冷却性能に余裕がある場合、通常のブーストクロックを超えて自動的に性能を引き上げる機能です。
従来の手動オーバークロックとは異なり、システム環境をリアルタイムで判断しながら動作するため、安定性を保ちながら性能を伸ばせる点が特徴です。
高品質な電源や冷却を組み合わせれば、4750Gの処理能力をさらに引き出せるため、コストを抑えつつ性能を追求したいユーザーにとって有効な機能となります。
Pure Power 搭載
Ryzen 7 4750Gは、省電力と効率的な動作を支える「Pure Power」技術を搭載しています。CPU内部に組み込まれた数百のセンサーが、電圧・温度・クロックをリアルタイムで監視し、状況に応じて最適な電力制御を行う仕組みです。
これにより、無駄な消費電力や発熱を抑えつつ、必要な性能は確保できるため、安定性と効率性を両立できます。ユーザーが特別な設定を行わなくても常時機能する点も特徴で、静音性や省エネ性を重視するPC構築において重要な役割を果たします。
Eco Mode(省電力モード)対応
Ryzen 7 4750Gは「Eco Mode(省電力モード)」に対応しており、標準のTDP 65W設定を45W相当に引き下げて運用することが可能です。
AMD公式ツール「Ryzen Master」やマザーボードのBIOSから簡単に切り替えができ、省電力性や静音性を重視するユーザーに有効な機能です。
性能はやや低下しますが、発熱の抑制や電力効率の改善に大きく貢献し、省スペースPCや長時間稼働する環境で特に効果を発揮します。高い性能を持ちながらも柔軟に消費電力を調整できる点は、Ryzen 7 4750Gを実用的かつ扱いやすいAPUにしています。
Unlocked仕様(倍率ロックフリー)
Ryzen 7 4750Gは、上位モデルと同様に倍率ロック解除された「Unlocked仕様」を採用しています。これにより、ユーザーはBIOS設定やAMD公式ツール「Ryzen Master」を用いてクロック倍率を調整し、オーバークロックによる性能向上を試すことが可能です。
もっとも、自動制御機能(PB2やPBO)が優秀なため、標準設定でも高い性能を発揮しますが、冷却環境や電力供給に余裕を持たせればさらなる性能を引き出せます。
オーバークロックの自由度を確保しつつ、安定性も維持できる仕様は、自作ユーザーにとってカスタマイズ性の高さを楽しめる要素のひとつです。
AVX2 / FMA3 命令セット対応
Ryzen 7 4750Gは、最新の拡張命令セットであるAVX2およびFMA3に対応しています。AVX2は従来より広い256bit幅で整数演算を効率的に処理でき、画像処理や科学技術計算、データ解析などで大きな効果を発揮します。
一方、FMA3(Fused Multiply-Add)は浮動小数点演算を効率化し、動画エンコードやシミュレーション処理で性能を高めます。
これらの命令セット対応により、Ryzen 7 4750Gは日常用途を超えた高負荷ワークロードにも対応可能で、APUでありながら幅広い計算処理を快適にこなせる点が大きな強みとなっています。
AMD StoreMI Technology 対応
Ryzen 7 4750Gは、AMD独自のストレージ高速化技術「StoreMI」に対応しています。これはSSDとHDDを組み合わせて1つの仮想ドライブとして扱い、SSDをキャッシュとして利用することでデータアクセスを大幅に高速化する仕組みです。
よく使うアプリケーションやファイルは自動的にSSD側に配置されるため、ユーザーは意識せずとも快適なレスポンスを体感できます。
大容量HDDのコストパフォーマンスとSSDの高速性を両立できる点が大きな魅力であり、特に4750Gを用いたコスト重視のPC構成や、ワークステーション用途において有効な機能です。
Radeon Vega 8(iGPU)搭載
Ryzen 7 4750Gは、統合型グラフィックスとして「Radeon Vega 8」を内蔵しています。8基のCU(Compute Units)を備え、最大2.1GHzで動作するこのiGPUは、従来のAPUに比べ描画効率が向上しており、フルHD解像度でのライトゲーミングや動画編集を外部GPUなしでこなせます。
省スペースPCやビジネス用PCにおいて、コストを抑えつつ一定のグラフィックス性能を確保できる点は大きな魅力です。また、マルチメディア処理や複数ディスプレイ出力にも対応しており、日常利用から業務用途まで幅広く活用可能です。
発覚している相性の問題
Ryzen 7 4750Gは、Zen 2世代のAPUとして多用途に使える高性能モデルですが、登場当初にはいくつかの相性問題が確認されています。
代表的なものとして、旧世代マザーボードでのBIOS未対応による起動トラブル、DDR4メモリの高クロック利用時に生じる不安定動作、冷却不足による高温化、そしてソフトウェアやドライバー側での最適化不足が挙げられます。
いずれも適切なBIOS更新やメモリ選定、冷却環境の強化、最新ドライバーの導入といった基本的な対策で改善が可能です。
本章では、Ryzen 7 4750Gで発覚している相性問題とその対策について解説していきます。
マザーボードBIOSとの互換性
Ryzen 7 4750GはZen 2ベースのAPUとして2020年に登場しましたが、既存のAM4マザーボード環境ではBIOSの対応状況によるトラブルが散見されました。
特にB450やX470といった旧世代チップセットでは、初期BIOSがAGESAの更新に追従しておらず、CPUを装着しても起動しない、あるいはiGPUが認識されないケースがありました。OEM先行販売という特殊な経緯もあり、当時は対応BIOSが十分に整備されていなかったことも影響しています。
対策としては、使用するマザーボードの公式サポートリストを確認し、事前にBIOSを最新バージョンへ更新しておくことが必須です。販売店によっては「Ryzen 4000Gシリーズ対応済み」と表記されたモデルもあるため、それを選ぶことでリスクを回避できます。
また、最新BIOSに更新することでメモリや拡張カードとの互換性も改善され、安定動作が期待できます。
メモリ相性
Ryzen 7 4750GはDDR4-3200を公式サポートしていますが、特に内蔵GPUを活用する場合、メモリ速度や相性がパフォーマンスに直結します。登場初期には、高クロックのOCメモリを利用した際にPOSTエラーやブルースクリーンが発生する事例がありました。
原因はマザーボードのBIOS側の調整不足やメモリICの特性によるもので、安定性を欠いた動作につながる場合があります。対策としては、まずBIOSを最新に更新し、マザーボードメーカーが公開しているQVL(動作確認済みメモリリスト)に掲載されているモデルを選択することが推奨されます。
さらに、APU構成ではメモリ帯域がiGPU性能に直結するため、必ずデュアルチャネルでの構築が重要です。安定性を優先する場合は公式サポート範囲のDDR4-3200を使用し、性能を追求する場合は安定動作が確認されたDDR4-3600程度まで試すと良いでしょう。
発熱と冷却環境
Ryzen 7 4750GはTDP 65Wの設計ですが、実際の使用環境ではCPUとiGPUを同時に活用すると消費電力が80Wを超えることもあります。
その場合、付属のWraith Stealthクーラーでは冷却が不十分となり、高負荷状態が続くと温度が80度を超えてクロック低下を招くケースがありました。
OEM提供が中心だったこともあり、メーカー製PCでは冷却設計に余裕がなく、サーマルスロットリングが発生する事例も報告されています。対策としては、ケース内エアフローを改善し、可能であればミドルクラス以上の空冷クーラーや簡易水冷を導入することが効果的です。
さらにRyzen MasterでEco Modeを利用したり、軽度のアンダーボルティングを行えば、性能を大きく損なわずに温度と消費電力を抑えることができます。長時間安定して利用するためには、冷却強化が実質的な必須対策といえるでしょう。
Windowsやソフトウェア側の最適化
Ryzen 7 4750Gは、CPUとGPUを統合したAPUという特性上、ハードウェアだけでなくソフトウェア環境の最適化も重要です。発売当初はOEM提供が中心であったため、ドライバーの配布が限定的で、Adrenalinドライバーが利用できず、内蔵GPUの最適化が不十分な環境が多く見られました。
その結果、描画性能が期待値を下回る、あるいは特定のアプリでクラッシュが発生する問題が確認されています。対策としては、AMD公式サイトから最新のチップセットドライバーおよびGPUドライバーを導入し、常に最新のWindows Updateを適用することが必須です。
また、電源プランを「Ryzen Balanced」に設定することで、クロック制御やスレッド割り当てが適切に行われ、CPUとGPUの両面でパフォーマンスが安定します。
さらに、最新アプリケーションではマルチスレッド最適化やGPUアクセラレーションを前提に設計されているため、ソフトウェアのバージョン管理も重要なポイントです。
総まとめ
Ryzen 7 4750Gは、Zen 2アーキテクチャを採用した「Renoir」世代を代表するAPUであり、8コア16スレッドのCPU性能とRadeon Vega 8を組み合わせたバランスの良さが光るモデルです。OEM向けに提供された背景から自作市場ではやや入手が難しい時期もありましたが、登場当初から省スペースPCやビジネス向けPCの構築において高い評価を受けました。
AM4プラットフォームに対応し、既存の環境を活かしやすい点も魅力です。シングルスレッド性能とマルチスレッド性能の両立により、日常用途から動画編集、クリエイティブ作業まで幅広くこなせます。さらに内蔵GPUのVega 8は、軽量なゲームやマルチメディア処理を外部GPUなしで実現し、コストパフォーマンスを重視するユーザーにとって強力な選択肢となります。
一方で、BIOS未対応による起動トラブルやDDR4メモリの相性、冷却不足といった課題が指摘されましたが、BIOS更新や安定したメモリ選定、適切な冷却対策により改善可能です。ソフトウェア環境を整備すれば、その性能を存分に発揮できます。
Ryzen 7 4750Gは「グラボ不要で汎用的に使える高性能APU」として、Zen 2世代を象徴する存在であり、現在でも十分に実用的な価値を持つ一基といえるでしょう。