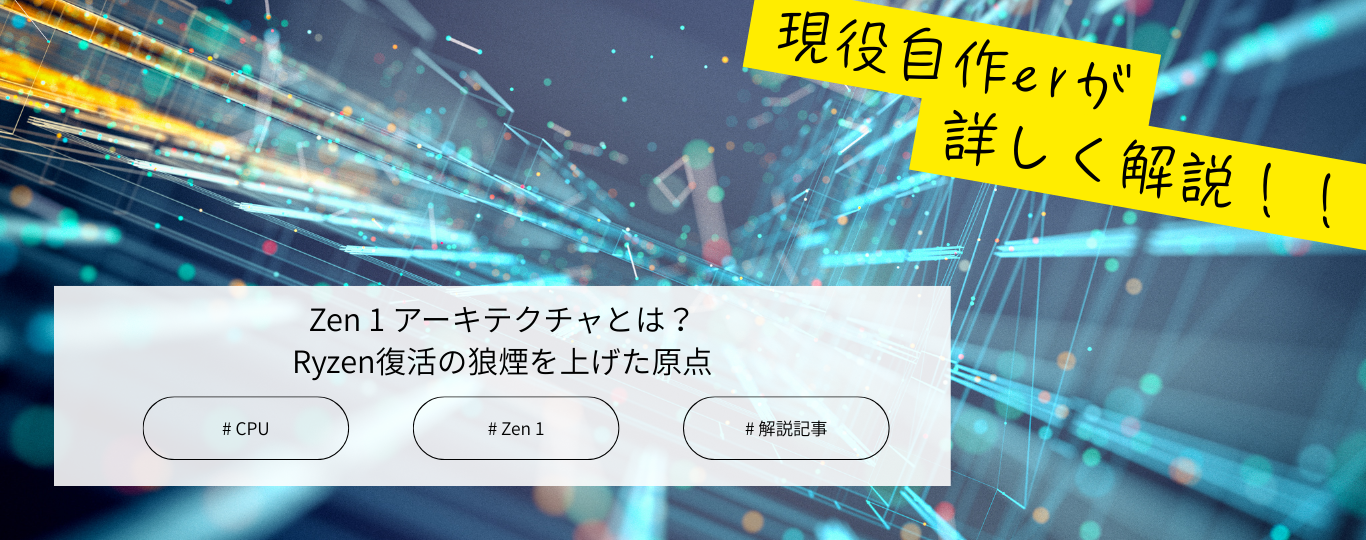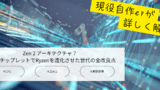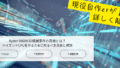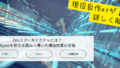どうも、jisa郎です。
2017年、AMDは長らくIntelに押され続けたCPU市場に劇的な変化をもたらしました。その立役者こそ、完全新設計の「Zen 1」アーキテクチャを採用した初代Ryzenです。
14nmプロセスで製造されたこの世代は、8コア16スレッドの同時マルチスレッディング(SMT)を実装し、当時としては驚異的なマルチスレッド性能を実現。さらにInfinity Fabricによる柔軟な内部接続構造、AVX2対応、Precision BoostやXFRによる自動クロック調整など、エンスージアストが求める要素を詰め込みました。
それまでの「廉価な代替品」というAMDのイメージを一新し、性能・価格の両面で市場を揺るがす存在となったZen 1は、以降のRyzen進化の出発点でもあります。
Zen 1 とは?
Zen 1アーキテクチャは、AMDが長年の低迷期を脱するために総力を挙げて開発した完全新設計のCPUコアです。 AMDはBulldozer系アーキテクチャの低IPCや高消費電力に苦しみ、ハイエンド市場でIntelに大きくシェアを奪われていました。
当時の製造パートナーであるGlobalFoundriesも最先端プロセスで後れを取り、競争力の回復は容易ではない状況でした。
そこでリサ・スーCEOは、既存設計の延命ではなく新アーキテクチャ+最新プロセスの同時導入という高リスク戦略を決断。2012年にジム・ケラー氏を中心とする新チームが発足し、IPC向上と電力効率の両立を狙ったゼロベース設計が始まります。
2017年3月、14nm FinFET(GlobalFoundries製LPP)と新インターコネクト「Infinity Fabric」を採用したRyzen 1000シリーズとして市場投入。最大8コア16スレッド構成、DDR4メモリ対応、SMT実装、そして攻めた価格設定が話題となり、自作PC界隈を席巻しました。
この成功は、その後のZen 2以降や3D V-Cacheといった革新技術へとつながる礎となり、Zen 1はAMD再生の象徴的世代として記憶されることになります。
Zen 1のコア設計の特徴
Zen 1アーキテクチャの真価は、単なるコア数やクロックの向上だけではありません。AMDはこの世代で、内部のパイプライン構造から命令スケジューリング、キャッシュ階層に至るまでを完全に再設計しました。
各コアは高効率な命令フェッチ機構と分岐予測器を備え、マイクロOPキャッシュにより不要なデコードを省略。整数演算ユニットと浮動小数点ユニットは独立して並列動作し、スループットを最大化します。
さらに「Infinity Fabric」による柔軟なコア間接続が、マルチコアの一体感を実現。このようにZen 1は、当時のAMDが抱えていた性能面での弱点を根本から解消し、次世代Ryzenの礎となるモダンなCPU設計へと生まれ変わったのです。
アーキテクチャ刷新(Bulldozerからの完全脱却)
Zen 1は、AMDが長年抱えてきた課題である「Bulldozer系アーキテクチャの限界」から完全に脱却するために生まれた、新時代のCPUコア設計です。
Bulldozer世代では、1モジュール内で2つの整数コアがFPU(浮動小数点ユニット)を共有する構造を採用していましたが、この方式はシングルスレッド性能の低下や負荷分散の非効率さを招き、競合のIntel製CPUに対して不利な状況を長く続ける要因となっていました。
Zen 1ではこの制約を根本から排除し、完全なフルコア設計へ移行。各コアが独立した整数ユニット、浮動小数点ユニット、キャッシュを持ち、全ての演算リソースを専有できる構造に生まれ変わりました。
さらに大きな進化として、SMT(Simultaneous Multi-Threading)に対応。1コアで2スレッドを同時実行できるため、スループットが向上し、マルチスレッド環境での性能が飛躍的に改善しました。このSMT実装は、既にIntelがHyper-Threadingで成功していた技術に対抗しつつ、AMD独自のリソース配分最適化を組み込んだもので、同時実行性能の効率は非常に高いと評価されます。
また、命令パイプラインも全面再設計されました。Bulldozerでは命令のフェッチ、デコード、スケジューリングの各段階でボトルネックが多く、IPC(命令あたりの実行効率)が低迷していましたが、Zen 1では新しい分岐予測器、マイクロOPキャッシュ、広帯域のフェッチ機構を導入。これにより、命令の取り込みから実行までの遅延を減らし、安定した高IPCを実現しました。
この刷新は単なる世代交代ではなく、AMDの設計思想そのものを変革するものであり、Zenアーキテクチャの礎を築く決定的な一歩となりました。
キャッシュ構造の刷新
Zen 1アーキテクチャは、AMDが長らく抱えていたキャッシュ効率の課題を根本から見直し、階層構造を大きく刷新しました。まず大きな特徴は、専用L2キャッシュの採用です。
Bulldozer系ではモジュール内の2コアが一部キャッシュや実行リソースを共有する構造であったため、スレッド間での競合やアクセス遅延が発生しやすい欠点がありました。
Zen 1ではこれを完全に解消し、各コアが独立した512KBのL2キャッシュを専有。これにより他コアからの干渉がなくなり、スレッドごとの安定性と一貫したアクセスレイテンシが確保されました。
次に、共有L3キャッシュの最適化です。Zen 1では4コア単位で構成されるCCX(Core Complex)ごとに8MBのL3キャッシュを搭載し、CCX内の全コアで共有できる形にしました。この設計は、大規模なデータセットやマルチスレッド処理においてデータの重複保持を減らし、キャッシュヒット率を高めます。
ただしCCXを跨ぐアクセスはInfinity Fabric経由となるため若干のレイテンシ増加があるものの、同一CCX内では高速かつ効率的なデータ共有が可能になっています。
さらに、キャッシュレイテンシの短縮もZen 1の重要な進化点です。L1キャッシュは命令用64KB、データ用32KBと大容量を維持しつつアクセス遅延を抑制。L2/L3キャッシュも回路設計の最適化によって、Bulldozer世代より大幅に低レイテンシ化しました。
この結果、メモリ階層全体の応答速度が向上し、メインメモリ依存度が減少。これらの刷新により、Zen 1はシングルスレッド性能とマルチスレッド性能の双方で競合に匹敵、あるいは上回る実行効率を実現しました。
新しい命令セット対応
Zen 1アーキテクチャは、AMDが長年Intelに後れを取っていた命令セット対応面でも大幅な刷新を果たしました。その中核となるのが「AVX2」「FMA3」「AES-NI」「SHA拡張」などの最新命令群への対応です。これらは単なるチェックボックス的な追加ではなく、実際のアプリケーション性能に直結する重要な機能でした。
まずAVX2(Advanced Vector Extensions 2)は、256ビット幅のSIMD(Single Instruction, Multiple Data)演算をサポートし、特に浮動小数点や整数ベクトル演算の並列処理に有効です。科学技術計算、動画エンコード、ゲーム物理演算など、マルチメディアやHPC分野で恩恵が大きく、Zen 1世代で初めて本格対応することで、競合IntelのHaswell以降と肩を並べられる基盤が整いました。
FMA3(Fused Multiply-Add)は、掛け算と足し算を1命令で同時に行う命令で、レイテンシ削減と演算効率向上に寄与します。これにより、機械学習や科学計算など繰り返し演算が多い処理でパフォーマンスが大きく向上します。
AES-NI(Advanced Encryption Standard New Instructions)は、ハードウェアレベルでAES暗号化/復号を高速化する命令群です。従来のソフトウェア処理に比べて圧倒的に高速で、VPN通信やディスク暗号化の処理負荷を大幅に軽減します。Zen 1ではAES-NIをフル実装し、セキュリティ性能を飛躍的に高めました。
さらにSHA拡張(Secure Hash Algorithm Extensions)は、ハッシュ計算をハードウェア支援することで、データ検証や署名生成といったセキュリティ関連処理を加速します。これにより、SSL/TLS通信やファイル整合性検証などの場面でもレスポンスが向上します。
これら命令セット対応により、Zen 1は従来のAMD CPUで弱点だった暗号化・復号、ハッシュ処理、並列浮動小数点演算といった分野で大幅な性能強化を果たし、ソフトウェア互換性の面でもIntelとの差をほぼ解消しました。結果として、エンタープライズからコンシューマまで幅広い用途で採用しやすいプラットフォームへと進化したのです。
Infinity Fabric の採用
Zen 1世代では、AMDが新たにInfinity Fabricと呼ばれる内部高速インターコネクトを採用しました。これは単なるバスの置き換えではなく、CPUコア群、メモリコントローラ、I/Oハブ、さらにはAPU構成時のGPUまでを統一的なアーキテクチャで接続する基盤です。
従来のように機能ごとに異なる専用リンクを個別制御するのではなく、全コンポーネント間のデータ転送と同期を一元管理できるのが大きな特徴です。
Infinity Fabricの採用により、コア間通信のレイテンシ低減とメモリ帯域の効率的利用が可能になりました。複数CCX(Core Complex)間のキャッシュコヒーレンシもこのFabric上で処理され、マルチコア化が進む中でもスケーラブルな性能を確保できます。
また、PCIeレーンやSATA、USBといったI/O経路も同じ統合ファブリック上で管理されるため、I/O性能とメモリ性能のバランスを柔軟に調整できる設計が可能となりました。
さらに、このInfinity Fabricはメモリクロックと密接にリンクしており、DDR4メモリ速度の向上がそのままファブリック帯域の拡大につながります。この性質は、OC(オーバークロック)愛好家にとって性能チューニングの新たな切り口となり、Zen世代以降のAMDプラットフォーム特有の調整ポイントとなりました。
結果として、Infinity FabricはZen 1の拡張性・性能・電力効率の根幹を支える要素となり、後のZen 2以降でも進化を続けるAMDの中核技術として定着していきます。
DDR4メモリ対応
Zen 1世代では、AMD CPUとして初めてDDR4メモリに公式対応しました。公式スペック上はDDR4-2666までのサポートとなっており、それ以前のDDR3世代と比べて帯域幅と動作効率が大きく向上しています。
特にマルチコア化が進んだZen 1では、コア間通信やメモリアクセスの性能がシステム全体のパフォーマンスを左右するため、高速メモリ対応は極めて重要な進化でした。
Zen 1の大きな特徴として、Infinity Fabricのクロックがメモリクロックに同期するという設計があります。Infinity FabricはCPUコア、メモリコントローラ、I/O、そしてAPU時のGPUまでを接続する内部インターコネクトであり、その動作速度はメモリクロックと1:1で連動します。
このため、メモリクロックを引き上げることで、コア間通信やI/O帯域も同時に向上し、システム全体のレスポンスやスループットが改善される傾向があります。
この設計は、オーバークロック愛好家やパフォーマンスチューニングを重視する自作erにとって大きな魅力でした。たとえば、公式サポートのDDR4-2666を超え、安定動作可能な範囲で高速メモリを使用すれば、理論上Infinity Fabricの帯域も同時に拡大し、ゲームやメモリ集約型アプリケーションで顕著な性能向上を狙えます。
一方で、Zen 1世代は高クロックDDR4の安定性にマザーボードやBIOSの完成度が大きく影響したため、OCを行う場合はメモリ互換リストやUEFI設定のチューニングが必須でした。この「メモリクロック=Infinity Fabricクロック」という構造は、Zen 2以降も引き継がれるAMDプラットフォームの特徴となります。
電力管理機能の刷新
Zen 1世代では、性能だけでなく電力効率の大幅改善が重要なテーマとなりました。その中核を担ったのが、「Pure Power」「Precision Boost」「XFR(Extended Frequency Range)」という3つの新電力管理技術です。
Pure Powerは、CPUダイ全体に配置された数百ものセンサー(電圧・温度・負荷)からリアルタイムにデータを取得し、動作電圧やクロックをきめ細かく最適化する技術です。これにより、必要以上の電圧供給や発熱を抑え、同一性能でも消費電力を削減できる仕組みを実現しました。
Precision Boostは、負荷状況に応じてコアクロックを25MHz刻みで自動制御する機能です。全コア負荷時と単一コア負荷時でクロックの最適化が行われ、ワークロードに応じたパフォーマンスの引き出しが可能になりました。これにより、旧世代のような大雑把なP-State切替から脱却し、よりリニアな周波数制御が実現しています。
XFR(Extended Frequency Range)は、冷却性能に余裕がある場合に限り、Precision Boostの上限をさらに超えてクロックを自動引き上げる仕組みです。高性能空冷クーラーや水冷システムを利用しているユーザーほど恩恵を受けやすく、ハードウェア環境に応じた自動OCのような動作が可能となりました。
これら3つの技術は連携して動作し、Zen 1を単なる「高性能CPU」ではなく、発熱と電力効率を両立するスマートなプラットフォームへと進化させました。この電力管理思想は、以降のZen世代でも改良を重ねながら継承され、AMDの省電力設計の基礎となっています。
Zen 1(3世代目)
デスクトップCPU
| モデル名 | C/T | クロックレート | L3 | TDP | ||
| ベース | ブースト | |||||
| LRyzen 9 | 1800X | 8(16) | 3.6 | 4.1 | 16MB | 95W |
| 1700X | 3.4 | 3.9 | ||||
| 1700 | 3.0 | 3.75 | 65W | |||
| Ryzen 5 | 1600X | 6(12) | 3.6 | 4.1 | 95W | |
| 1600 | 3.2 | 3.7 | 65W | |||
| 1500X | 4(8) | 3.5 | 3.9 | |||
| 1400 | 3.2 | 3.45 | 8MB | |||
| Ryzen 3 | 1300X | 4(4) | 3.5 | 3.9 | ||
| 1200 | 3.1 | 3.45 | ||||
APU
| モデル名 | C/D | クロックレート | グラフィックプロセッサ | L3 | TDP | ||||
| ベース | ブースト | モデル | コア | GHz | |||||
| Athlon | 200GE | 2(4) | 3.2 | – | Vage3 | 3CU | 1.0 | 4MB | 35W |
| 220GE | 3.4 | ||||||||
| 240GE | 3.5 | ||||||||
| 3000G | 3.5 | 1.1 | |||||||
| Ryzen 5 | 2400G | 4(4) | 3.5 | 3.8 | Vage8 | 8CU | 65W | ||
| Ryzen 3 | 2200G | 4(8) | 3.6 | 3.9 | Vage11 | 11CU | 1.25 | 65W | |
まとめ
Zen 1アーキテクチャは、単なる新CPUではなく、AMDの歴史を塗り替えた転換点でした。
Bulldozer系で苦しんだ低IPC・高消費電力からの脱却、そしてハイエンド市場で再びIntelと真っ向勝負するための完全新設計。その挑戦は、リサ・スーCEOの経営判断と、ジム・ケラー氏率いる開発陣の情熱によって結実しました。
14nm FinFETプロセスの採用、Infinity Fabricによる統合インターコネクト、DDR4-2666対応とFabricクロック同期、高効率な電力管理(Pure Power / Precision Boost / XFR)、そしてAVX2やAES-NIといった最新命令セットの実装。
これらの要素が融合し、2017年3月に登場した初代Ryzen 1000シリーズは、最大8コア16スレッド構成で圧倒的なマルチスレッド性能を誇りつつ、コストパフォーマンスでも市場を揺るがしました。
自作PCマニアにとってZen 1は、「AMDが本気を出せばここまでやれる」という証明であり、以降のZen 2、Zen 3、Zen 4、Zen 5へと続く快進撃の礎です。
今振り返れば、その革新性とリスクを恐れない姿勢こそが、現在のAMDブランド価値を形作った最大の要因だったといえるでしょう。Zen 1は、技術史においても経営史においても、Ryzenの始まりを告げた不朽の第一歩なのです。
初代Zenは、AMDが再び高性能CPU市場に返り咲くための原点でした。
この基盤をさらに磨き上げ、7nmチップレット構造やPCIe 4.0対応を実現したのがZen 2アーキテクチャです。
初代Zenは、AMDが再び高性能CPU市場に返り咲くための原点でした。
この基盤をさらに磨き上げ、7nmチップレット構造やPCIe 4.0対応を実現したのがZen 2アーキテクチャです。