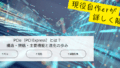どうも、jisa郎です。
CPUとGPUを一体化した「iGPU(統合型グラフィックス)」は、省スペースPCやノートPCだけの技術と思われがちです。しかしAMDが手掛けるiGPUは、その常識を覆してきました。
単なる映像出力装置ではなく、ゲームや映像編集、GPUアクセラレーションを積極的に活用できる性能を備え、アーキテクチャも世代ごとに進化。
Llano世代の黎明期からGCNアーキテクチャを経て、最新Ryzen APUに搭載されるRDNA系コアまで、その進化はGPU単体市場をも意識した設計思想が垣間見えます。
本記事では、AMD iGPUの歴史的背景から内部構造、アーキテクチャ別の特徴、活用シーンまで徹底解説し、「CPUに内蔵されたGPU」の奥深さに迫ります。
歴史および背景
AMDのiGPU(統合型グラフィックス)の歴史は、2011年の「Llano」APUから始まります。当時はCPUとGPUを単一ダイに統合し、低消費電力ながらエントリー向けGPU性能を提供することが狙いでした。
Llanoでは当時のRadeon系GPUアーキテクチャ「TeraScale」を採用し、従来のオンボードグラフィックスに比べて大幅な描画性能を実現。これにより、軽量ゲームやHD動画再生が十分に可能となりました。
その後、2012年の「Trinity」以降はGCN(Graphics Core Next)アーキテクチャを導入し、DirectX 11以降の3D描画性能やGPGPU用途に対応。HSA(Heterogeneous System Architecture)構想のもと、CPUとGPUのメモリ空間を統合する方向へ進化しました。
2017年の「Raven Ridge」ではZen CPUコアとGCNを組み合わせたRyzen APUが登場し、デスクトップ用途でもiGPUがゲームや制作作業を支える存在に…。
最新世代ではRDNA 2/3アーキテクチャを採用し、ハードウェアレイトレーシングやAV1デコードなど単体GPU級の機能を搭載。こうしてAMD iGPUは、省電力ノートPCからゲーミングPCまで幅広く採用される存在へと成長しました。
どういう構造か?
AMDのiGPUは、CPUダイ上にGPUコア(CU:Compute Unit)を統合した構造を持ちます。物理的には同じシリコン上にCPUコア群とGPUコア群が配置され、内部インターコネクトを介してメモリコントローラやキャッシュ階層を共有します。
これにより、外部PCIe接続の単体GPUと比べてデータ転送のレイテンシが極めて低く、軽量処理では効率的に動作します。
グラフィックス部分はRadeonアーキテクチャをベースとし、世代によってGCNやRDNAの命令セットと演算ユニット構造を採用。例えばRDNA世代ではWave32実行、改良されたパイプライン、ハードウェアレイトレーシングユニットなどが搭載されています。
メモリはシステムRAMをGPUメモリとして共有する「UMA(Unified Memory Architecture)」方式を採用。これによりVRAM専用チップは不要ですが、帯域はシステムメモリの速度に依存します。APUのメモリ性能はiGPUの性能に直結するため、高速なDDR4やDDR5、さらには低レイテンシの設定が推奨されます。
また、ディスプレイ出力回路(Display Engine)や動画エンコード・デコード用のVCE/VCNユニットも統合され、単体GPUに近いメディア処理能力を実現。全体として、AMDのiGPUはコンパクトな構造でありながら、マルチメディアや軽量3D処理に必要な要素を一通り備えています。
前型との違い
AMDのiGPUは世代ごとにCPUアーキテクチャと同時進化しており、前型からの変化はGPUアーキテクチャ・製造プロセス・メモリ規格の進化が大きな軸となります。
初期のAPU(例:LlanoやTrinity)ではGPU部は古いVLIW型Radeonを搭載し、DirectX対応やGPGPU性能は限定的でしたが、GCN世代以降は並列演算性能が飛躍的に向上し、OpenCLやDirectComputeなど汎用計算への応用も現実的になりました。
また、前世代ではPCIeレーン数やディスプレイ出力規格(HDMI・DisplayPort)の対応範囲が制限されていたのに対し、新世代では最新の映像規格(HDMI 2.1、DP 1.4/2.0)をサポートし、高リフレッシュレート・高解像度環境にも対応。
さらに、製造プロセスの微細化により、GPUコア数や動作クロックを引き上げながらもTDPを抑えることに成功しています。
メモリ面でも、DDR3からDDR4、そしてDDR5への移行が進み、UMA方式の帯域不足が徐々に緩和。これにより、前型ではボトルネックになりやすかったメモリ速度が、最新世代では高速グラフィックス処理にも耐えられる水準に達しました。
総じて、前型から現行型への進化は「単なる性能向上」だけでなく、グラフィックス機能の実用性と互換性の幅を広げ、単体GPUを使わないライトゲーミングや動画編集にも十分対応できるレベルに押し上げた点が大きな違いです。
iGPUを設計しようとした理由
AMDがiGPUを搭載したAPU型CPUを設計し続ける理由は、大きく分けて3つあります。
第一に市場ニーズの多様化です。すべてのユーザーが高性能な外部GPUを必要としているわけではなく、ビジネス用途・家庭用PC・小型PC市場では、省スペース・省電力で高いグラフィックス機能を持つ統合型が好まれます。これにより、エントリーからミドルレンジまで幅広い価格帯で競争力を確保できます。
第二に技術的優位性の確立です。CPUとGPUを同一ダイに統合することで、メモリ共有による低レイテンシ通信や消費電力の最適化が可能になります。特にAMDはRadeon由来のGPUアーキテクチャを統合できるため、グラフィックス性能において他社のiGPUより優位に立ちやすく、映像処理やGPGPU分野でも活用範囲を拡大できます。
第三に次世代技術の布石としての役割です。APUはHSA(Heterogeneous System Architecture)やCXLなど、CPUとGPUが密接に連携する技術の実証プラットフォームとしても機能します。これにより、将来的な統合アーキテクチャやAI向け計算環境にスムーズに移行できる基盤を整えられます。
総じて、iGPU搭載型は単なる低コストモデルではなく、AMDが目指す「CPUとGPUのシームレス統合」戦略の中核を担う存在であり、同社の長期的なプラットフォーム進化の要となっているのです。
まとめ
AMDのiGPUは、単なる内蔵グラフィックスにとどまらず、同社のプラットフォーム戦略を象徴する存在です。初期は省コスト・省スペースPC向けの付加価値として位置づけられていましたが、Radeonアーキテクチャの統合やメモリ帯域の最適化により、軽量なゲームや映像編集、GPUアクセラレーションを必要とする業務までこなせる水準に進化しました。これにより、外部GPUを搭載せずとも快適なPC体験が得られる環境を提供しています。
さらに、iGPUはCPUとGPUの連携強化という大きな技術トレンドの中核でもあります。共有メモリを活用した低レイテンシ通信、電力制御の最適化、そしてHSAやCXLといった次世代規格への対応など、将来的な統合アーキテクチャへの布石としても機能しています。この方向性は、省電力かつ高性能を求めるノートPC市場や組み込み機器、クラウド環境において特に有効です。
結果として、iGPU搭載のAMD CPUは、初心者のエントリーPCからコンパクトなクリエイティブマシン、さらには企業向け業務端末まで、幅広い領域で採用されています。単なる「コスト削減策」ではなく、AMDが描くCPUとGPUの融合戦略の最前線を担う重要な技術基盤であることは間違いありません。