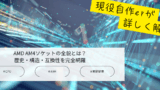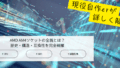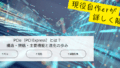どうも、ジサ郎です。
DDR5・PCIe 5.0時代の幕開けと共に登場したAM5ソケットは、AMDが未来世代への足掛かりとして送り出した新世代CPU土台です。
LGA1718方式を採用し、高速I/Oと大容量メモリ帯域を前提とした設計。USB4や最新の電力管理技術も視野に入れ、長期運用を想定しつつも次世代性能を最大限引き出すための構造的刷新が施されています。
AM4で培われた長期互換性の理念を引き継ぎつつも、PCI Express 5.0、DDR5メモリといった最新規格をネイティブでサポートし、帯域・レイテンシの両面で飛躍的な進化を実現。LGA1718という新しいピンレス構造を採用することで、信号密度と電力供給能力を大幅に強化し、TDP170WクラスのハイエンドCPUにも余裕を持って対応します。
さらに、Infinity Fabricの改良により、CPUコアとI/Oダイ間の通信効率が向上し、高クロックDDR5や高速ストレージの潜在能力を引き出せる設計となっています。
AM5は単なるソケット刷新ではなく、Zen 4以降の世代がフル性能を発揮するための必然として生まれた存在です。本記事では、その歴史的背景から構造的特徴、AM4との相違点、そしてAMDがこの形に辿り着いた理由まで、マニア視点で深く掘り下げていきます。
歴史および背景
AM5ソケットは、AMDが2022年9月にZen 4アーキテクチャとともに投入した最新世代のデスクトップ向けCPUソケットです。長年続いたAM4からの世代交代であり、物理的な互換性を切り捨てる代わりに、新しい規格への対応を優先しました。
その最大の背景は、DDR5メモリおよびPCI Express 5.0といった次世代インターフェースをサポートするためのピン配置・電気仕様の刷新です。AM4時代の長期サポートは評価が高かったものの、次世代技術の受け入れには根本的な設計変更が不可欠でした。
また、AM5はLGA(Land Grid Array)方式を採用し、従来のPGA(Pin Grid Array)から大きく構造を変えることで、耐久性と高ピン数対応力を確保しました。この背景には、より多くの電力供給ラインと信号経路を確保し、高性能CPUの動作安定性を向上させる狙いがあります。
AMDはAM5を少なくとも2025年後半以降まで継続サポートする方針を明言しており、これによりユーザーは将来のCPUアップグレードを見据えた長期的なプラットフォーム運用が可能になります。
どういう構造か?
AM5ソケットは、LGA1718と呼ばれる1718接点を持つLGA方式を採用しています。これにより、CPU側にはフラットなパッドが配置され、マザーボード側ソケットに金属ピンが内蔵される構造です。
LGA方式はインテルのメインストリーム向けソケットで長年採用されており、ピンの曲がりによるCPU破損リスクを軽減しつつ、より高密度な配線を可能にします。1718ピンは、DDR5メモリチャネルやPCIe 5.0レーン、拡張された電力供給経路を支えるための重要な要素であり、特に高性能なマルチコアCPUや将来のAPUにも十分な帯域と安定性を提供します。
また、AM5は従来のヒートスプレッダー形状をほぼ維持しており、冷却互換性に配慮。AM4対応クーラーの多くが流用可能で、ユーザーは新ソケットへの移行コストを抑えられます。
ソケット周辺部にはより大型のVRM(電圧レギュレーターモジュール)を搭載可能な設計が取られ、OC(オーバークロック)や長時間高負荷時の電力安定性も確保されています。
前型との違い
AM5はAM4と比較して、多方面で大きな刷新が行われています。まず最大の違いはメモリサポートで、DDR5専用となりDDR4との互換性がありません。
これにより、より高いクロックと帯域幅、低消費電力動作を実現しています。次にPCI Express世代が5.0に進化し、GPUやNVMe SSDにおいて将来の帯域需要にも余裕を持たせています。
また、AM4がPGA1331ピン構造だったのに対し、AM5はLGA1718方式を採用し、ピン数が大幅に増加。これによりI/O信号や電力供給ラインが拡張され、高性能化と安定動作を両立しました。
さらに、USB4やDisplayPort 2.0などの最新規格もマザーボード設計次第で対応可能になっており、I/O面での将来性が飛躍的に向上しています。
一方、物理的なCPU互換性はなく、AM4用CPUはAM5マザーボードに装着できませんが、この割り切りによって次世代技術を最大限活用する設計が実現しています。
このソケットで設計しようとした理由
AMDがAM5を設計した理由は、次世代アーキテクチャとI/O技術を完全に活かすためです。DDR5とPCIe 5.0は、今後10年近くにわたりPC市場の基盤となる規格であり、これらに対応するには電気的・物理的な設計刷新が避けられませんでした。
特にDDR5は高クロック化に伴い信号品質の確保が難しく、ピン配置や配線長の最適化が必須。加えて、マルチコア化と高TDP化が進む中で、より多くの電力を安定供給するためのVRM設計やパワーデリバリラインの増加が必要でした。
AM5ではLGA方式に移行することで、これらの課題を解決しつつ、耐久性と将来の拡張性を確保しています。さらに、AMDはAM4で培った長期サポート戦略を踏襲しつつも、物理互換性を捨てることで最新規格の導入を優先しました。
この戦略は短期的には移行コストを伴いますが、中長期的にはプラットフォーム全体の競争力と安定性を高める狙いがあります。
まとめ
AM5は、AMDが次世代PC市場に向けて投入した長期運用前提のプラットフォームであり、その設計思想は「将来の拡張性」と「最新規格の完全活用」にあります。
DDR5メモリとPCIe 5.0に対応するためのLGA1718構造は、高帯域・高安定性を実現し、マルチコア時代の高性能CPUを余裕をもって支える仕様です。
AM4時代の長寿命サポート方針を踏襲しつつも、互換性を切り捨てたのは技術的進化を阻害しないためであり、これによりUSB4やDisplayPort 2.0などの最新I/Oも柔軟に取り込めます。
また、冷却互換性やVRM強化といったユーザー配慮も残されており、自作PC愛好家からワークステーション利用者まで幅広く対応可能です。今後のZen 4以降の世代CPUにとって、AM5は単なるソケットではなく、性能ポテンシャルを最大限引き出すための基盤といえるでしょう。
長く使われたAM4の特徴と歴史を振り返り、AM5との比較ポイントも紹介しています。