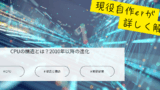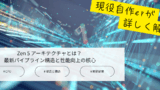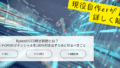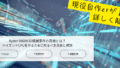どうも、jisa郎です。
Zen 4は、単なる「クロック向上と微細化の世代」では終わらない、緻密な設計思想が詰まったアーキテクチャです。フロントエンドからバックエンド、キャッシュ階層、I/O制御に至るまで全域を磨き上げ、パイプラインの流れを徹底的に最適化。
分岐予測の精度向上、Op Cache効率化、L2キャッシュ倍増、AVX-512対応。
それぞれは数値上の改善に見えますが、総合すると高クロック維持性能や長時間負荷での安定性に直結します。Zen 3の完成度を基盤に、あらゆるワークロードで隙のない性能を発揮するよう進化したZen 4は、単なる世代交代ではなく「息の長いプラットフォーム」として自作PCマニアの心を掴む存在です。
そんなZen 4について、徹底解説していきます。
Zen 4とは?
Zen 4は、AMDが2022年9月に投入したRyzen 7000シリーズに採用されたマイクロアーキテクチャです。製造はTSMCの5nmプロセス(CCD)と6nmプロセス(IOD)の組み合わせで行われ、前世代Zen 3からIPCを約13%向上させつつ、最大クロック5.7GHzという高周波数動作を実現しました。
ソケットは新たにAM5を採用し、DDR5メモリとPCI Express 5.0への対応を果たしたことも大きな転換点です。さらに、IODに統合されたRDNA 2ベースのiGPUにより、GPU非搭載モデルの汎用性も向上しました。
Zen 4のコア設計の特徴
Zen 4のコア設計は、単なるプロセス微細化やクロック向上に留まらず、パイプライン全域にわたる緻密な再設計が光る世代です。フロントエンドから実行ユニット、キャッシュ階層までの連携を徹底的に磨き上げ、高クロック動作時でも命令供給とデータ転送のボトルネックを最小化。
さらにAVX-512対応やL2倍増といった大きな目立つ変更の裏に、分岐予測精度やOp Cache効率化など“数値には現れにくい職人技”が詰まっています。この精密な設計思想こそ、Zen 4を真に理解すべき理由です。
フロントエンドの進化
Zen 4のフロントエンドは、命令取り込みからデコードまでの経路を効率化し、高クロック動作時でもスループットを維持できる設計へと進化しました。最大の強化点は分岐予測の精度向上で、L1 BTB(Branch Target Buffer)のエントリ数が拡張され、L2 BTBも強化。
これにより分岐予測ミス率が低下し、分岐ミス発生時のパイプラインフラッシュ回数が減少します。結果として、特に短いループ処理や条件分岐の多いコードで性能の安定性が向上しました。
命令フェッチ部も改良され、帯域幅が広がることで1サイクルあたりの命令供給量が増加。これによりバックエンドが空待ち状態になる機会が減少します。また、オプキャッシュ(Op Cache)の構造最適化により、マイクロOPヒット率が高まり、デコード段の負荷軽減にも貢献しています。
これらの改良は、単発のIPC向上だけでなく、高クロック動作時の効率維持やAVX-512などの広帯域演算命令供給に直結しており、Zen 4の総合性能向上の土台となっています。
デコード部の強化
Zen 4のデコード部は、命令をx86からマイクロOP(μOps)に変換する処理効率を高めることで、バックエンドへの命令供給を安定化させています。最大デコード幅はZen 3同様1サイクルあたり4命令ですが、複合命令の分解アルゴリズムが改良され、より少ないクロックで複雑な命令をμOps化できるようになりました。
これにより、デコード段のボトルネックが緩和され、Op Cacheからの供給時にもスループットが向上します。さらに、Op Cache自体のヒット率を高めるチューニングが施され、同じ命令列を繰り返すループ処理やゲームの描画ループなどでデコード負荷が減少。
結果として、デコード段を経由しない高速なμOps供給経路の利用頻度が増え、全体の命令処理効率が改善されています。高クロック動作時にはデコード段が律速要因となるケースが多いですが、この最適化により、Zen 4はAVX-512や複雑な浮動小数点演算を含む命令でも安定した処理が可能となりました。
これらの強化は、IPCの向上だけでなく、広帯域命令処理を必要とする次世代ワークロードにも対応できる基盤となっています。
スケジューラと実行ユニット
Zen 4のスケジューラ部は、命令の発行効率と待ち時間短縮を目的に最適化されています。レイテンシが短くなり、発行可能スロット数も拡大したことで、並列処理時に命令が待機キューで滞留する時間が減少。結果として、より多くの命令を同時に実行ユニットへ送り込める構造になりました。
整数演算ユニット(ALU)はZen 3同様4基のままですが、スケジューラからの供給効率向上によってスループットは確実に改善しています。一方、浮動小数点演算(FPU)側では256ビット幅のAVX-512命令をデュアルパイプで処理する構成を採用し、消費電力を抑えつつ高帯域のベクトル演算に対応。
これが科学技術計算や3Dレンダリング、AI推論など計算負荷の高い処理において、高い持続性能を支える要因となっています。さらに、整数/浮動小数点の双方で拡張精度演算(FP64)の処理効率が高まり、HPC分野での計算時間短縮にも貢献。
スケジューラと実行ユニットの改良は、Zen 4が高クロック動作と安定したスループットを両立する上で欠かせない柱と言えるでしょう。
ロード/ストア
Zen 4のロード/ストア部は、メモリアクセスの並列性と応答速度を向上させるために複数の改良が施されています。ロードキューのエントリ数が従来よりも増加し、同時に処理できるロード要求の本数が拡大。
これにより、帯域の広いDDR5メモリやPCIe 5.0接続SSDといった高速デバイスからのデータ取得でも、実行ユニットへの供給が滞りにくくなりました。また、ストア側もバッファ効率が見直され、書き込み処理の待ち時間が短縮。
これが、大量のデータを頻繁に更新するワークロードでの処理効率向上に直結しています。L1データキャッシュは32KBと容量こそ変わらないものの、レイテンシ低減と帯域幅拡大によりヒット時の応答性が向上。さらに、L2キャッシュは容量が1MBへと倍増され、より多くのデータをプロセッサ内部に保持できるため、メインメモリアクセスの回数を減らす効果があります。
こうしたロード/ストア経路の最適化は、単に帯域を広げるだけでなく、キャッシュ階層全体との連携効率を高めることで、CPU全体の命令実行パイプラインをより安定的に稼働させる基盤となっています。
キャッシュ階層
Zen 4のキャッシュ階層は、高クロック化に伴うメモリアクセス遅延を最小限に抑えるため、各レベルでレイテンシ短縮と容量拡大が図られています。L1データキャッシュは容量32KBのままですが、アクセスレイテンシがわずかに短縮され、帯域幅も拡大。
これにより、ロード/ストアユニットが頻繁に利用する小規模データの取得速度が向上しました。L2キャッシュは従来の512KBから1MBに倍増され、かつレイテンシを極力抑えた設計となっており、特に大規模ループ処理や分岐予測成功率の高い連続アクセス時に大きな効果を発揮します。
L3キャッシュはCCDあたり最大32MB構成を継承しつつ、Infinity Fabric経由のアクセス効率が最適化され、マルチCCD構成時のクロスアクセスに伴うレイテンシを軽減。これにより、2CCDモデルでもゲームやクリエイティブ用途でのスループット低下が抑えられています。
また、DDR5の広帯域を活かすため、キャッシュ階層全体でプリフェッチアルゴリズムも調整されており、メモリアクセスの先読み精度が向上。結果として、単一スレッド性能の底上げだけでなく、マルチスレッド環境でもスムーズなデータ供給が可能になっています。
新機能とI/O周りの強化
Zen 4世代では、CPUコアアーキテクチャの刷新だけでなく、I/O周りにも大きな進化が施されています。まず新機能として注目されるのがAVX-512命令セットの正式対応です。
これにより、AI推論や科学技術計算、動画エンコードといった広帯域ベクトル演算を、従来のAVX2よりも高効率かつ高速に実行可能となりました。また、Precision Boost Overdrive(PBO)やEco Modeといった電力管理機能も強化され、用途に応じた柔軟な性能・消費電力の最適化が可能です。
I/O面では、メモリがDDR5に対応し、最大帯域幅が大幅に向上。加えて、PCI Expressは第5世代に対応し、最新の高性能GPUやNVMe SSDに対して、より広い転送路を確保できます。USBもUSB 4およびDisplayPort Alt Modeをサポートし、外部接続の拡張性と汎用性が向上しました。
これらのI/O拡張は、単なる規格更新に留まらず、Zen 4の高クロック動作やキャッシュ階層の効率化と組み合わさることで、実アプリケーションにおけるデータ転送のボトルネックを低減。結果として、ゲーミングからHPC、クリエイティブワークまで幅広い分野での総合性能を底上げしています。
Zen 4(6世代目)
デスクトップCPU
| モデル名 | C/T | クロックレート | L3 | TDP | ||
| ベース | ブースト | |||||
| Ryzen 9 | 7950X3D | 16(32) | 4.2 | 5.7 | 128MB | 120W |
| 7950X | 4.5 | 64MB | 170W | |||
| 7900X3D | 12(24) | 4.4 | 5.6 | 128MB | 120W | |
| 7900X | 4.7 | 64MB | 170W | |||
| 7900 | 3.7 | 5.4 | 65W | |||
| Ryzen 7 | 7800X3D | 8(16) | 4.2 | 5.0 | 96MB | 120W |
| 7700X | 4.5 | 5.4 | 32MB | 105W | ||
| 7700 | 3.8 | 5.3 | 65W | |||
| Ryzen 5 | 7600X3D | 6(12) | 4.1 | 4.7 | 96MB | 120W |
| 7600X | 4.7 | 5.3 | 32MB | 105W | ||
| 7600 | 3.8 | 5.1 | 32MB | 65W | ||
APU
| モデル名 | アーキテクチャ | クロックレート | グラフィックプロセッサ | L3 | TDP | |||||
| 4 | 4c | |||||||||
| C/T | C/T | ベース | ブースト | モデル | コア | GHz | ||||
| Ryzen 7 | 8700G | 8(16) | – | 4.2 | 5.1 | 780M | 12CU | 2.9 | 16MB | 65W |
| Ryzen 5 | 8600G | 6(12) | – | 3.6 | 5.0 | 760M | 8CU | 2.8 | ||
| 8500G | 2(4) | 4(8) | 4.3 | 740M | 4CU | |||||
| Ryzen 3 | 8300G | 1(2) | 3(6) | 4.1 | 4.9 | 2.6 | 8MB | |||
まとめ
Zen 4は、単なるクロックアップや微細化の進化にとどまらず、アーキテクチャ全体を隙なく磨き上げた世代です。フロントエンドからキャッシュ階層までの各部が強化され、命令の供給・発行・実行の流れがよりスムーズになりました。
特にL2キャッシュの倍増やAVX-512対応は、単発のベンチマークスコアだけでなく、長時間の負荷や特殊ワークロードにおいても安定した性能を発揮します。I/O周りもDDR5やPCIe 5.0、USB4など最新規格を揃え、将来のパーツ選択の自由度を大きく広げました。
これは単に最新対応というだけでなく、帯域や遅延の改善が内部設計と噛み合うことで、リアルな使用感にも直結する強化です。長年自作を続けてきたマニアから見れば、Zen 4は完成度の高さと拡張性を両立させた、非常にバランスの良い世代といえます。
Zen 3からの移行でも恩恵は確実に体感でき、Zen 2以前からであればなおさら。スペック表では見えにくい細部のチューニングが、日々の作業から趣味のゲームまでを底上げする。そんな堅実かつ実用的な進化がZen 4の本質です。
Zen 4の成果を受け継ぎ、さらにIPCと効率を高めたのが次世代Zen 5アーキテクチャです。